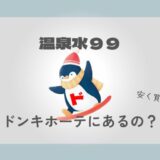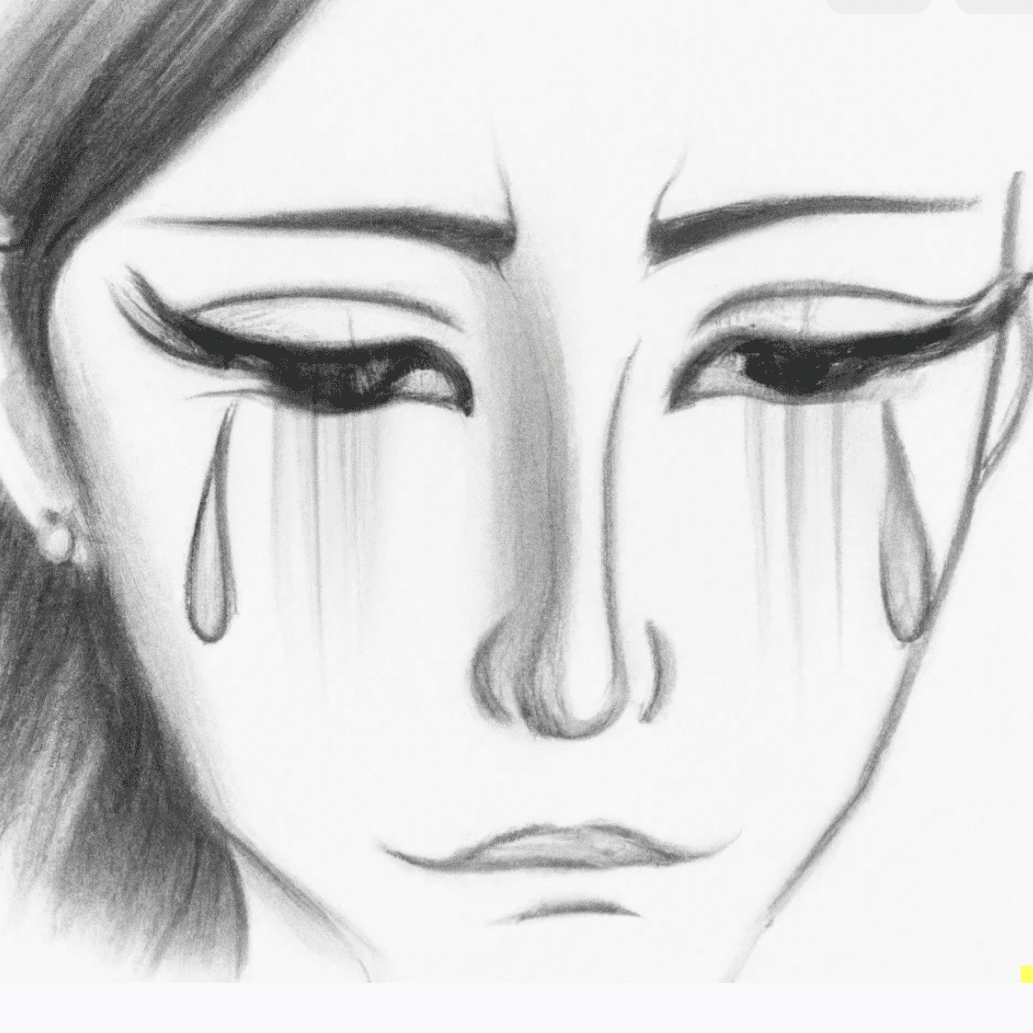
「無添加にこだわるママ友がうざい!」
ズバリ、そう言われる理由は3つあります。
しかしそのまま反論してしまうと、それに対し相手も反論し、討論になってしまいかねません。
正しく相手の話を聞いて、こちらの主張を伝えることでお互いの主張を整理することができます。
後半では、その対処法もお伝えします。「対処法を知りたいよ!」と思う方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
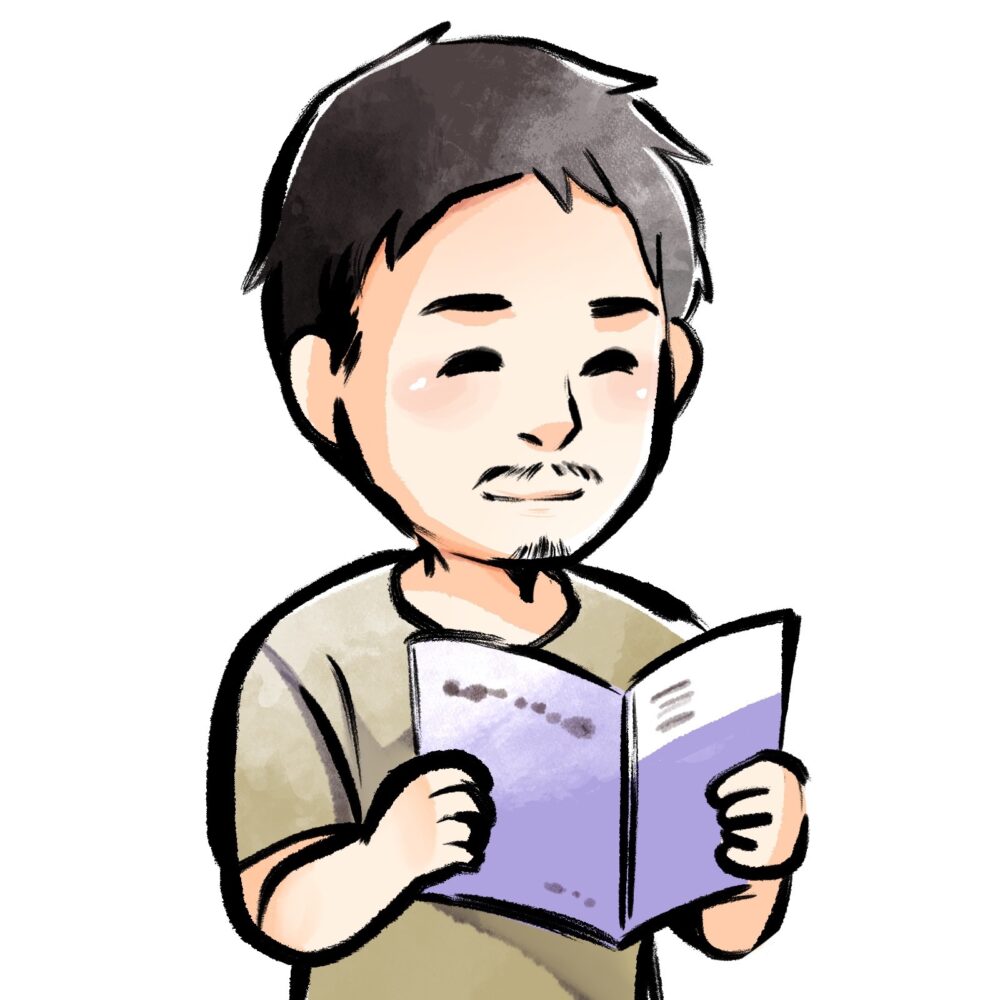
今まで添加物は気にしてませんでしたが、知識を増やして無添加のものを選んで購入するようになりました。
とはいえ無添加を人に強要することもなく、自分の家族のみ情報を共有しています。誰でも指摘されるのは不快ですからね。
ただお互いの観点を整理するのは大切なので、この記事を作成しようと思いました。最近の楽しみは、オーガニックスーパーに行っていろんな商品を見ること。
それでは解説していきます。
無添加ママが「うざい」といわれる3つの理由
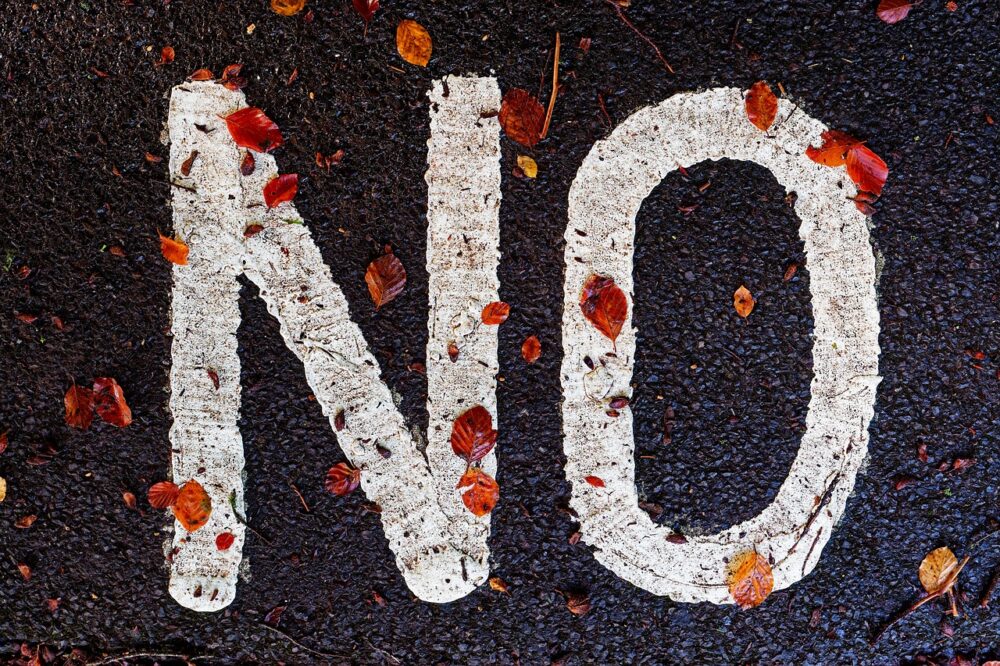
ここでは、指摘される人の心境について解説します。指摘されたことによって、どんなことを感じているのでしょうか?確認していきましょう。
アドバイスというと一見良いことに思うかもしれませんが、言われた本人からすると「余計なお世話」と感じる方もいます。
そもそもアドバイスをするのにも技術は必要です。伝え方を間違えれば、受け取る人の経験や判断を否定しているように受け取るかもしれません。
例えば、あなたが何か達成したいことがある場合に、他人から自分のやり方について指摘されると否定されたように感じるかと思います。
つまり、聞き手を尊重していないように感じるわけです。
過保護である点も問題でしょう。というのも「子供には、加工食品食べさせない方がいいよ!」と相手のことを思い、発言していたとしても言われた人にとっては嫌悪感が生まれるかもしれません。
心配だからこその発言というのはわかりますが、聞き手にとっては食卓のメニューを否定されたようにとらえかねませんよね。また干渉されていると感じるかもしれません。
その結果、育児のスタイルへの対立が生まれ、不快に感じるママもいるはず。お互いを尊重し合い、理解することが大切です。
自己主張が強いママは他の意見や考えを軽視し、自分が正しいと思っている知識を押し付ける傾向にあります。
たとえその知識が正しいとしても、押し付けられた人は反発するか心にモヤモヤが残ります。他のママの意見を尊重しなければ、円滑なコミュニケーションにはならないでしょう。
誰でも自分の常識を否定されるのは、気分が悪いはずです。SNSのインフルエンサーであればその主張に対し、賛同する人たちがファンになります。
しかし、ママ同士のコミュニケーションでは主張し合うのは円満とはならないのです。
無添加にこだわるママが思っているコト2つ

無添加ママは、どんな目的があって指摘しているのでしょうか。確認していきましょう。
無添加にこだわるママは、添加物を避けたいと思っています。なぜなら、食品の闇を知っているから。その知識は、自ら勉強しなければ辿り着くことはないでしょう。
テレビやニュースではいうはずもありません。書店に行けばその種の書籍はたくさんあります。しかしながら、皆知らないんです。
その状態で子どもたちが「おいしい、おいしい……」って食べてるのを見るのは正直、気分の良いものではありません。
だからこそ、皆に気付かせたいという想いからアドバイスや指摘という形で伝えているのではないでしょうか。
添加物にこだわらないママは、食品の原材料を見ません。理由は、体に悪いと思っていないからです。実際にスーパーに買い物に行くと、原材料を見ている方は見当たりません。
添加物のなかにも「食べてもいいもの」「食べてはいけないもの」があります。実をいうと、知れば怖くて食べられない添加物もあるんです。
それだけに添加物の怖さを知らないママの意識を高めたいと思うのではないでしょうか。そうすれば少しでも子どもたちを救えるのではないかと考えているかもしれません。
いずれにしても人を否定したいわけではなく、その危機感を伝えたいのだと思います。
【対処法】無添加ママの行動や発言で「うざい」と感じた時には?

まずは、相手を理解することが大事です。本当にあなたのことを気にかけ、伝えたいことがあるかもしれないからです。たしかに「うざい」と感じることはあります。
しかし、最初から相手の意見を遮断してしまうと1つも知識として残ることはありません。
あなたに加工食品の闇に気付いてほしい……
この添加物だけは避けた方がいい……
など相手の言葉には深い意味があると考え、聞き入れてみることでお互いの理解を深めることができるかもしれません。
相手の気持ちを理解ができたら、あなた自身の考えを率直に伝えることが重要です。言葉にしない限り、相手はあなたの考えや感情を把握することができません。
例えば、あなたが「細かい事は気にしたくない」と思っていたとしても、伝えていなければ当然、相手に伝わる事はありませんよね。
そうすれば「この人は些細なことを気にしない人なんだ」と理解してくれるはずです。また相手の気持ちを理解した上で、興味のある話なら質問してみましょう。
新たな知識を得ることができるかもしれません。
あなた自身の考えを伝えた上で、それでもまたアドバイスや指摘をしてくるのであれば一度、距離を置きましょう。あなたと相手の考えの違いというのは、簡単には埋まらないからです。
友人との関係で意見や感情がすれ違い、相手が何かを誤解してしまった場合、冷静になる時間が必要です。どちらかが感情的になればコミュニケーションが難しくなる。
冷静な状態になり考えることで解決する手段がみつかることがあります。だからこそ時間を作るのも大切なのです。
無添加ママとうまく付き合うためのコツ
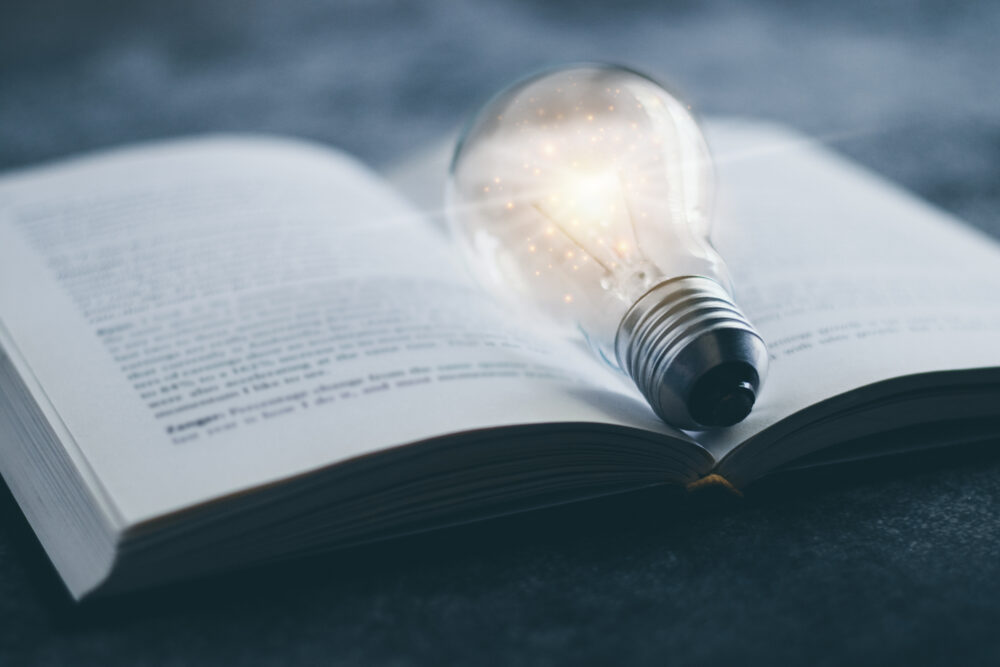
価値観は、人それぞれ違います。つまり、常識も人それぞれということ。
お箸を使う国もあれば、手で食べる国もある。
お好み焼きとご飯を一緒に食べる地域もあれば、
食べない地域もある。
夜にお風呂に入る人もいれば、朝に入る人もいる。
何が正しいなんてないと思うんです。むしろ皆んなが違うから楽しくないですか?であるからこそ相手を尊重し、理解し合うことが大切です。
「自分自身が信じてきた知識」は正しいか考えたことはあるでしょうか?
意外とその情報には、両親に教えてもらった、みんながしているからといった根拠のないものがあります。
もし仮に、両親やみんなが間違えているとすればあなたの知識は誰かの思い込みによって作られたものかもしれません。
新しい情報や違う観点を受け入れることで成長には欠かせないステップを踏むことができるでしょう。
ちなみに、私も人の意見を聞くのが苦手で自分が信じていることが正しい!と思っていましたが、色んな観点で物事を見れるようになってからは、知識や情報が雪だるま式に増えていきました。
相手からアドバイスや指摘をされたら、その情報は正しいのか確認する必要があります。
その知識は誰が言ってて、どこに書いてあるのか、またはどんな本で見たのかを教えてもらいましょう。
そうすることで情報の信頼性や背景を理解することができます。
例えば、健康に良い食事法についてです。その情報が専門家によるものであれば信頼できますよね。一方でテレビ番組の街頭インタビューでの意見であればどうでしょうか?
つまり専門的な知識や科学的な裏づけがあるかどうかを確かめることが重要であり、不可欠です。
添加物が気になりだしたら最初にすること

本のパッケージには、著者の伝えたいことが込められています。それを見るだけでも本の雰囲気は伝わってくるはず。
その中には警鐘を鳴らすワードであったり、私たちの常識をくつがえすような一文が書かれていたりします。
本を書いている人がどれくらいの専門性があるのか確認しておきましょう。信頼できる情報なのかわからないですからね。
こんな事は無いとは思いますが、あまり研究されてない方が書いた情報なら信頼できないじゃないですか。
本の信頼性を見極める上で、著者の経歴や学歴、研究や経験など確かめることは大切です。
パッケージ、著者を見て興味が出たら、目次を見るだけでも知らない知識が書かれています。全部を読む必要なんてありません。
ただあなたが気になる部分だけをみればいいんです。それだけで知識は1つ得ることができるんです。
下記には、私のオススメの本をご紹介しています。パッケージだけでも見てくださいね。
【食品添加物】オススメ本7選
まとめ
無添加ママがうざい!って思ってたけど実は、私たちに警鐘を鳴らしているのかもしれません。
もし簡単に人の常識を変えたり、伝えることができたらトラブルは減ると思います。ただしそれにはお互いが尊重し合うことが大切。
それが難しいからこそ、本記事を書かせていただきました。実は私も危険な食べものをあなたに食べさせたくないという気持ちがあります。
ぜひ書店にお立ち寄りする際には、添加物の書籍コーナーでパッケージだけのぞいてみてくださいね。